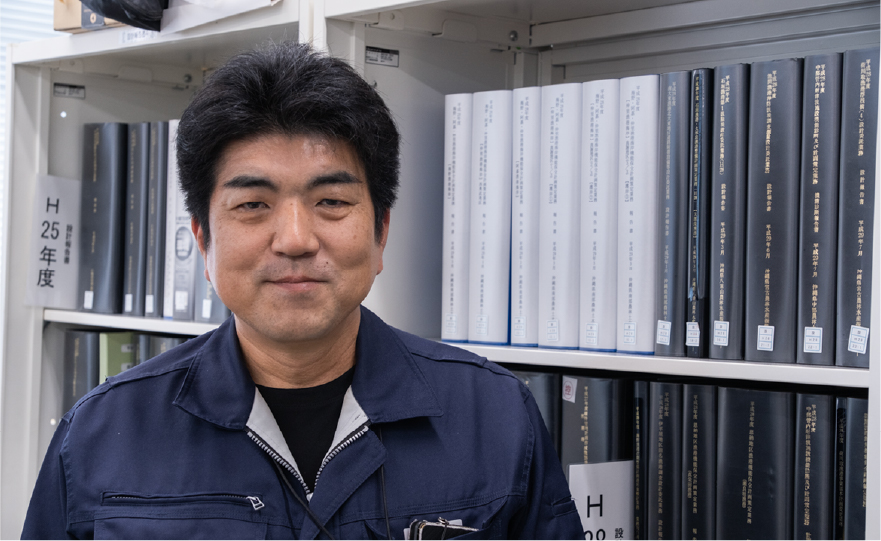
設計業務はとにかく奥が深いですからね。安心して仕事を後進に預けていけるように技術や考え方をどんどん継承していきたいです。
大栄コンサルタントに入社後、設計業務を中心にさまざまな仕事に携わってきた25年目のベテラン技術者。上司としての仕事への向き合い方、豊富な経験に基づく部下の育成や技術継承の考え方、技術者としての将来像について語ってもらいました。
Profile
設計部 部長
- 入社年
- 2001年4月(25年目)
- 出身校
- 琉球大学大学院 理工学研究科
仕事へのプレッシャーは常にありますが
気が付けば、会社と社会に貢献できている
という実感が持てるようになっていました。
― 唐突ですが(笑)。失礼ながら、『当社一筋』の部長にあえてお聞きします。 今までで、会社を辞めたいと思ったことはありますか?もちろん、言える範囲で(笑)。
設計部 部長:いやいや、それは当然ありますよ(笑)。20年以上前の話ですけど、入社して2、3年目ぐらいのときは、何度か辞めたいと思ったことがありますね。なんというか、仕事が妙に難しいなと感じてしまったり、なかなか進めきれなかったり。特にきつかったのは、設計基準に標準的な考え方が無いような、イレギュラーな問題や課題に直面することが増えてきたころでした。これって、打合せの期日までに解決できるんだろうかとか、工期までに作業は終わるんだろうかとか、いろんなプレッシャーを感じてましたね。
― いや~、部長と同年代の技術者ということもあって、私にはすごく共感できます。。。その後はどうですか?
設計部 部長: 仕事が難しいなと感じることは、今でもよくありますよ。設計業務はとにかく奥が深いですからね。ですけど不思議なもので。今となっては、仕事が大変で辞めたいと思うことは、全然ないですね。家族や同僚の生活のためということは言うまでもないんですけど。ありがたいことに、会社と社会に貢献できているな、という実感をいつしか持てるようになったことが、大きいですかね。もちろん、部長という立場ですから、責任感からのプレッシャーは常に感じてますけど。
実務を伴わない設計の知識は頭に入りにくい。
まずは、最低限のことを伝えてから仕事を任せ
重要なタイミングではしっかり打合せをしています。
―部下の育成についてです。ご自分のためにも会社のためにも、仕事をどう効率的、効果的に覚えていってもらうかが重要ですよね。どんな風にされていますか?
設計部 部長: 経験者にはわかることなのですが、設計業務では技術体系が複雑でその範囲も広く、内容が多岐にわたります。また実務上は、座学では補えないようなイレギュラーなことやケースバイケースの対応が、キーポイントになるんです。なので今のところは、頭から一つ一つ座学で伝えるのは効果的ではないなと。正直なところ、当社独自の体系的な教育プログラムといったものも整備していません。ただし当社では、外部研修を積極的に活用していて、設計だけによらず、社会人のマナー、SDGs、その他周辺知識に関するものまで業務時間内に含めて、仕事扱いにしています。もちろん、参加費や交通費など研修に関する費用も会社が負担しています。
―OJT(実務を通じた訓練)については、どんな風に考えていますか?
設計部 部長: いったんは、最低でもここまでは伝えておいた方がよいな、というところまで説明するように留めて、任せるようにしています。そのあとは、同じような業務内容だとしても、人によって伝えるタイミングや内容は全然違ってくるんですね。ですので、担当者が質問してくれたとき、私がどうしても必要と考えたとき、その都度、できるだけ多くの時間を割いて打合せするようにしてます。最近だと、静穏度解析の業務で初めて主担当になってもらった例があるんですけど、よい仕事をしてもらってますよ。あと、これは自身の体験談でもあるんですけど。経験値が違う先輩の視点で必要と思うことを、先回りしてたくさん伝えようとしたところで、やっぱり実務を伴わない知識は頭に入りにくいんですよね。どうしても、大半のことは右から左に流れてしまうので、時間的にも精神的にも効率的とは言い難いなと。上手に教えられる人がうらやましいです(笑)。
― 次は、すごく現実的な話をお聞きします。CADのソフトにはいろいろと種類がありますよね。転職を考えるベテラン技術者にとって、どのCADソフトをメインで使っているかのというのは、案外、ボトルネックになるんじゃないかと思いまして。
設計部 部長: 当社では、オープンCADのBVCADとHOCADの2種類をメインで使ってます。例えば、沖縄県の業務ではBVCADで納品する必要があります。私は、BVCADよりもHOCADが使いやすいので、HOCADで作ったものをBVCADに変換することで対応してます。確かにCADは、ソフトが違うと印刷のやり方すらわからないほど操作性が全然違っていて、全く使いこなせないことだってありますからね。
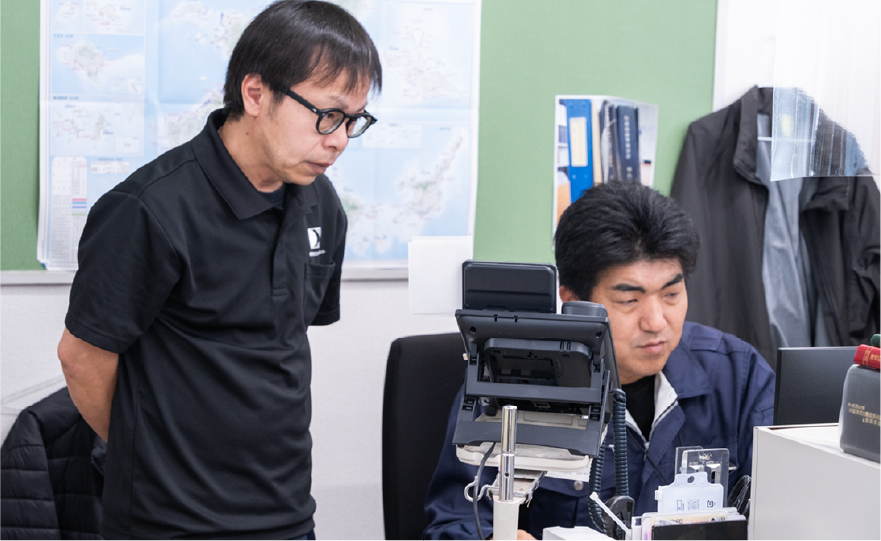
安心して仕事を後進に預けていけるよう
技術や考え方をどんどん継承していきたいです。
―将来に向けて、技術継承をどんな風にイメージしてますか?
設計部 部長: 自分が退職したり一線を退いたりということをイメージしながら、今のうちから安心して仕事を後進に預けていけるよう、技術や考え方をどんどん継承していきたいですね。設計の仕事は奥が深くてしんどい時もありますけど、検討結果をまとめていくプロセスは充実感があって楽しいです。あと、自分が設計に関わった構造物の実物を見ると、何とも言えない満足感があるんですよね。構造物の規模が大きいとか小さいとかは、あんまり関係ないんです。ベテラン技術者のあるあるだと思いますけど、それだけに、どうしても仕事や技術を抱え込んでしまいがちだと思うんです。ですから、極端に言えば、近いうちに引退するんだ!というぐらいの覚悟をもって取り組むことで、本気モードにしていきたいと考えてます。
効率的かつ完成度の高い仕事ができる
技術者を追求していきたいです。
―もう十分ベテランの領域だと思っていますけど、あえてお聞きしますね。技術者としては、どんな風に追求していきたいですか?
設計部 部長: 設計の仕事は技術基準だけでは完結しません。決して自己満足というわけではなくて、論文や類似事例などをどれだけ調べて、どれだけ自信を持って最適解と思える成果を出せるかが大切だなと感じてます。ベストに近いと思える結果が導き出せたときはもちろん嬉しいですから、より効率的に、納得できるような完成度の高い仕事ができる技術者を追求していきたいですね。



